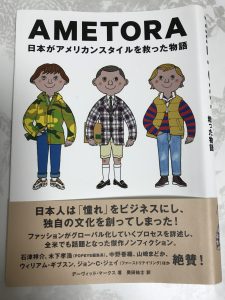
秋を通り越して、初冬のような気候です。
慌ててちょっと厚めのジャケットやコートを引っ張り出している方も多いのでは?
先日会った友人は極薄のダウンを着込んでいました。
そんな今日このごろ。
日本在住のアメリカ人ジャーナリストが書いた、
とってもおもしろい日本ファッション史の本に出会いました。
「AMETORA」(デーヴィッド・マークス 著 奥田祐士 訳 DU BOOKS)。
著者は、ハーバード大学で東洋学を学んでいたものの、
来日するまでは「アメリカ人が世界で一番クール」と思っていたそうです。
クールとは「カッコいい」とかそんな意味です。
ところが、日本に来てまわりを見渡せば、ワカモノたちはみんなオシャレ。
アメリカンよりジャパニーズの方が全然クールじゃん!
というわけでカルチャーショックを受け、
日本のファッションについて調べ出し、卒論まで書いてしまったそうです。
日本の青少年たちのファッションの夜明けは、
前回の東京オリンピック直前の頃。
戦後の日本が見事に復興を遂げ、先進国の仲間入りも間近!
という姿を世界に見せるために、なんとかしてこれを成功に導くため、
官民一丸となって全力をそそいでいた矢先。
銀座のみゆき通りにヘンテコな格好の若者が数百人も集まって、
たむろしているという事態が勃発しました。
襟にボタンのついたワイシャツを着て、
(当時、ボタンダウンはまだ一般に普及していませんでした)
ツンツルテンのズボンを履き、
中にはスネまでの丈のズボンを履いた者もいる。
若者たちは週末になるとみゆき通りに集まり、何をするでもなくたむろしている。
当時のおじさんたちに理解できなかったファッションは
『アイビー・ルック』というものでした。
そこでオリンピックに向けてヘンテコなワカモノたちを排除するため、
私服警官たちが彼らを大量に検挙して一掃したといいます。
少なくともオリンピックが終了するまでは、
みゆき族もおとなしくしていたようです。
あれから50年余り。
オリンピックの閉会式に首相がサブカルのシンボルであるマリオになって登場する。
今やサブカルは日本を代表するビジネスのひとつであり、
クールジャパンの担い手です。
今ならみゆき族も街から一掃されることなく、
ダイバーシティ、日本のシンボルのひとつとして
積極的に活用されていたでしょうに。
時の流れを感じさせます。
日本も世界も年を重ねて熟して来たといえます。
アイビー・ルックの故郷はご存知のようにアメリカです。
1954年、ハーバード大学をはじめとした8校でフットボール連盟が結成され、
各校が蔦(アイビー)をシンボルにしていたことから、
アイビーリーグと名付けられ、大学生たちのキャンパスファッションが、
アイビー・ルックと呼ばれるようになりました。
日本では1964年に創刊された平凡パンチが、
「アイビー・ルック」の特集記事を組んだのがブームの発端といわれています。
ボタンダウンのシャツに三つボタンのジャケット、細身のコットンパンツ、
ローファーを履いて、しわしわの紙袋を脇に抱える。
当時、アイビールックを世に広めた「VAN」のアイテムを着るのが、
みゆき通りに集まるワカモノたちのステイタスでした。
そのロゴを冠した紙袋を脇に抱えて持つという点を見ても、
紙袋さえカッコいいものに変身してしまうという、
当時のワカモノたちの憧れの強さがうかがい知れます。
当時の大人たちにヘンテコ扱いされたアイビー・ルックも、
今やメンズファッションの正統派です。
そもそも、この、ジャケットとボタンダウンシャツをベースにした、
アメリカの大学生ファッションである『アイビールック』を日本に紹介し、
当時のワカモノのファッションに革命をもたらしたのが、
ヴァン ヂャケット、VANの社長だった石津謙介(1911-2005)でした。
岡山の裕福な家に生まれ、確かな審美眼と天性の鋭い感覚に恵まれていた石津さんは、
第二次大戦後、米国東海岸の名門大学を卒業したアメリカ人兵士の通訳を担当し、
伝統的な大学生ファッションの魅力やスタイルを学んだといいます。
1950年代半ばにヴァンヂャケットを設立。
VANを通してもたらされるファッションアイテムは、
昭和30年代のワカモノたちの心を鷲掴みにしました。
戦後の混乱がようやく収まって、高度経済成長期にさしかかり、
これから新しい世界がはじまるんだという期待に満ちていたワカモノたちに取って、
VANをはじめとしたブランドのアイビールックはまさに新しい世代のシンボルであり、
ワカモノたちしか手に入れられない最強のファッション的武器であったはず。
それゆえ石津謙介は一人のデザイナーでアパレルブランドの社長であるというより、
日本のメンズファッションに革命をもたらした、
ファッションの神様といわれている存在になったのです。
“1965年には、長男の石津祥介、くろすとしゆき、長谷川元、林田昭慶の
4名で著したファッション誌「TAKE IVY」は、時を経て欧米のファッション関係者の間で
注目されるようになり、2010年にアメリカ合衆国において、アシェット婦人画報社から
英語版が出版され、翌2011年にはオランダ語版と韓国語版が出版された。
ニューヨーク・タイムズは2009年6月17日付の記事で「TAKE IVY」を紹介し、
” a treasure of fashion insiders “「ファッション関係者の宝」と評している”
(出典:wikipedia)
つまり、かつて日本に輸入されたアイビー・ルックは、
いつしか本国でもお手本とするべき規範がくずれてしまって、
今や、日本発の「TAKE IVY」をはじめとしたアイビー・ルックの解釈やスタイルが、
本国でお手本にされているというわけなのです。
昔ロンドンで、タキシードの際のリボンタイの結び方を、
その場にいたイギリス人の6〜7人の男の子たちは誰も知らなくて、
日本人の超おしゃれな男の子が指導していたことがありましたが、
やっぱり日本はあなどれないファッション先進国なのかも。
ところで、その本の中では、その後、ヒッピースタイルも含めて、
日本の若い男子のメンズファッションは、
常にアメリカ文化から影響を受けていたと著者はいいます。
一方、女子は確かに、常にパリやらロンドン、ミラノと言った、
ヨーロピアンスタイルを取り入れてきました。
そうして、アメリカ産のシャツやジーンズを模倣していた日本はそれを極め、
不朽の名作ジーンズ、リーバイス501のステッチの数さえ正確に数えて、
すべて本物そっくりに仕上げているうちに、
ついに日本人は、仕上がりもクオリティも追い越してしまった、
今や岡山を中心とした縫製工場で生産されるジーンズやデニム地は、
世界一だと著者は書いています。
ジーンズやデニムをはじめ、気づけば日本のファッションは世界をリードしていて、
世界中のクリエーターやファッションモンスターが注目しています。
いつ頃から、日本がファッションリーダーのひとりになったのでしょう?
はじめて訪れた70年代初期のロンドンでは、何も感じませんでした。
とはいえ、ブレイク直後のデビッドボウイの伝説のコンサートで彼は、
山本寛斎のポップ&近未来的歌舞伎イメージの衣装を採用していて、
それが、宇宙から来たロックミュージシャンというストーリーで展開していたボウイに
すごく似合っていました。とはいえ、パントマイムを取り入れたシアトリカルな表現を
用いるボウイだから、カンサイを選んだのであって、
まだ、一般的なロックミュージシャンや若い世代が、
日本のデザイナーやファッションをリスペクトしたり注目したりという
時代ではなかったと思います。
風が変わってきたのは80年代に入った頃。
ロンドンで出会う若い子達はほぼ全員、
日本のファッションやサブカルに興味を抱いていました。
みんながトーキョーに行きたがっていて、
遠路はるばるロンドンまでやってきている者にとっては、
へー、そーなの?みたいな複雑な気分。
なので帰国時には、過去2回訪れたロンドンから帰国する際には抱いたことのない
「トーキョーかあ、楽しみ!」という思いまで抱いたほどです。
その後はロンドンの友達から「子どもがドラゴンボールにはまったので、
なんでもいいからグッズを送ってくれない?」と頼まれたり。
かつて、日本と欧米の関係は、こっちから見ると近いけど、
向こうから見ると遠い、みたいな面があったと思います。
最近は同じくらいの距離になって来たような。
そして、熱心で緻密な調査と知的な考察で書かれたこの本を読んで改めて思ったことは、
「知ることは近づくこと」であるということ。
日本がリーバイス501を徹底的に研究して熟知し、近づき、やがて肩を並べたように、
何かにこだわって知り尽くすことは、進歩への大事なステップですよね。
かくして、VANがもたらした国産メンズファッションのポリシーと気骨は、
今も土井縫工所はじめ、国内の心あるブランドに根を張っています。
そんな土井縫工所には世界をリードするデニム地と世界に名だたる生産地となった、
岡山の縫製工場で産まれるデニムシャツのシリーズがあります。
起毛素材のアイテムは、初冬に嬉しい・優しいぬくもりで、
袖を通したとたん、身も心もおしゃれに暖めてくれますよ。
*追記
日本のワカモノたちがアイビーをはじめアメリカのファッションを取り入れ始めたのは、戦後のこと。
それまでの日本の洋装の歴史は、文明開化以降、フランスや英国といったヨーロッパのスタイルを取りれて発達してきました。1964年からはじまったアイビールックはその後アメリカンカジュアルとして日本市場に定着。メンズファッションの一部先端がアメリカンテイストからより英国やイタリアを意識しはじめたのは、1970年代頃からだったかも知れません。さらに、ヨーロピアンテイストで解釈したアメリカンカジュアルも、イマドキの失敗しないコーディネートのひとつです。
