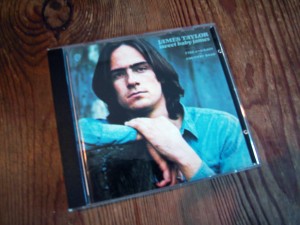いつまでも寒いと思っていたら、今日は3月の陽気だそうです。
近所では梅の花が咲き始めていたし、
あちこちで木々の枝の新芽が膨らんでいます。
もうすぐいっせいに花が開くのだろうと思うと、心が弾んでくるし、
自然はいつも元気をくれます。
♪重いコート脱いで出かけませんか?
というのは、キャンディーズの往年のヒットソングの名フレーズ。
服が薄くなると、なんだか気分まで軽くなりますよね。
冬の間、重宝していたダウンやカシミア、ウールやツイードなどのコートとも、
そろそろ、しばしのお別れです。
春先のコートはスプリングコートとも呼ばれます。
暖かい中に時折まだ肌寒い日もあるのがこの時期の特徴。
とくに梅雨の頃は予想以上に寒い日もあります。
春先と秋口に重宝するのが薄手のコートですが、
春専用に、ちょっと明るい色調のものを一枚持っておくのもおすすめです。
トレンチコート型やステンカラーのマッキントッシュ型、ピーコート型などは、
ビジネスにもカジュアルシーンでも着られるので、
淡いベージュやブルー系、少しピンクがかったグレー系などを選べば、
スーツにも合うし、ジーンズスタイルもスタイリッシュに決められそうです。
着丈は長いものより七分丈のほうが、
コーディネートの着回しがしやすいので、よりおトクといえそう。
たとえば、コートの中では最もフォーマルな格付けといわれる、
英国紳士御用達のチェスターフィールドコートなどは、
(あの人気TVドラマ「相棒」の杉下右京愛用のタイプです)
ロング丈の冬物だと、中は三つ揃いの英国調スーツでキメたい所ですが、
コットンやリネン素材で七分丈の春仕様のものなら、スーツにはもちろん、
ロンドンストライプやデニム素材のドレスシャツと合わせて爽やかにキメられます。
ボトムはジーンズにローファーなんかを合わせれば、
たちまち粋なヨーロピアンスタイルの完成です。
いずれにしろ、春仕様のコートは比較的ベーシックなデザインがおすすめ。
着る期間も短いので、あまり頻繁に買い換えないと思うし、
なるべく長く着られるようにするためです。
といっても、「定番の形だから10年も20年も持つ」と思って、
バブルの頃に奮発して購入した、
海外一流ブランドのスーツやコートが、
今となっては肩幅デカ過ぎ、身頃のシルエットがどうにも変、
などという理由で着られなくなっている中高年の方も多いのでは。
第一、体のシルエットが激変して着られない、という場合も。
ともあれ、まあ、2013年現在の定番におけるトレンドは、
肩が極端に大きいとかはないので、
少なくともあと3年は着られるんじゃないでしょうか?
3年後に極端に肩幅が狭い服が流行っている、
あるいは肩がむき出しの服が流行っている、
なんてことになっていた場合はお許しを。
で、ステンカラーやチェスターフィールドのようなキマジメな印象のコートの中は、
ピンク系やブルー系の、明るい色彩のドレスシャツを合わせたり、
赤やグリーンなどの差し色が効いたニットを合わせたりして、
一点、華やかさを加えてみましょう。
春らしくて、キマジメなコートとのギャップに女子ゴコロがそそられます。