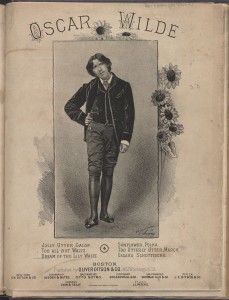まだまだ残暑が厳しいものの、
まだまだ残暑が厳しいものの、
夕暮れの早さに秋を感じます。
夏休みが終われば、秋の夜長がはじまりますね。
最近、ホテルのブライダル担当の方に取材することがあったのですが、
昨今の結婚式のトレンドは手作り感ということらしいです。
かつて、ホテルでの結婚式といえば、
広いバンケットルームに新郎新婦が座る、一段高いメインテーブルがあり、
ゲストが座る円卓や長テーブルが配置されていました。
親戚や恩師、会社の上司や同僚、友人たちの来賓の挨拶が続き、
ケーキカットにキャンドルサービス、というのが定番でした。
余興といえば友人のコーラスかギター演奏、手品くらい。
私は友人の結婚式で、
司会が往年の人気グループサウンズのボーカルだったことがあり、
「♪おまえのすべて〜」という大ヒット曲を生で聞けた時は、
ちょっと感動しましたが。
バブルの頃はかなり大仕掛になった余興やショーアップが、、
90年代に入ると次第に沈静化し、
中期からのウエディングはおしゃれなカフェやレストランで、
クールに催す地味婚がトレンドになってきました。
あるいは都会や高原にあるロマンティックなウエディング系教会や専門施設で、
別世界感満載な式をあげるとか。
一生に一度(の予定)のことですから、
新郎新婦(特に新婦さん)の壮大なドリームの実現でいいと思うのですが。
で、最近のトレンドはホテルでなく、
一軒家感覚のレストランやゲストハウスであげたいという意識があるらしく、
ホテル側も戸建感覚の式場を新設したり企業努力を重ねているようです。
私が取材したところでは「一軒家風のアイアンゲート」
「ゲストをお出迎えできるエントランスホール」
などがセールスポイントになっていました。
そして、ゲストとより親密な時間がもてるように、
余興は減る傾向にあり、
新郎新婦やゲスト間のトークタイムが多く設けられるのが時流だとか。
さらに、ウェディングの大切なポイントであるケーキも
新婦または新郎新婦による手作り、というのが増えているんだそうです。
さすがにケーキはパティシエにお任せして、
ヴィジュアル効果やおいしさを保証したというカップルでも、
手作りマカロンなど、一品手作りを加えて、しかも、
新郎新婦でそれをゲストたちに手渡しするのが今風とのこと。
引き出物にしても、新婦のお兄さまが焼いた器や、
新郎のお母さまが織った麻のテーブルナプキン、などというのが登場したり
ウエルカムボードをカップルの家族が手作りするのはもはや定番とか。
当人たちどころか、家族もうかうかしてはいられません。
そして、極めつけは、新婦のブーケを新郎が手作りするというのが、
最近人気の企画なのだとか。
その際、新郎のタキシードの襟につけるブートニアもペアで作るのだそうです。
なんか、ぶっとい指でブーケやブートニアを作っている新郎の姿を思い浮かべると、
微笑ましくも、もはや新婚家庭のパワーバランスが思い浮かぶ気がします。
中には新婦のドレスを手作りしちゃったという強者もいるようです。
(デザイナーとかでなく、普通のサラリーマンだったらしいです)
とにかく、家族や友人の絆をさらに強める、
というのが昨今のウェディングのキーワードのようですが、
どんなスタイルになっても「新婦一人勝ち」という状況は変わらないかも。
ともあれ、フォーマルなシーンで襟に花を飾る場合、
コサージュっぽく作りこんだものより、
みずみずしさを生かした生花をシンプルに飾るというのが、
よりスタイリッシュな気がします。