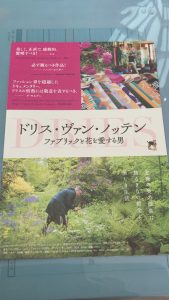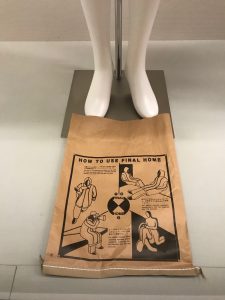もはや初夏を思わせる日差しに、輝きを放つ新緑。
風も心地よく、一年でも一番快適な季節になりました。
新卒の方々や、移動、転勤などで新しい環境を迎えた方々も
そろそろ馴染んできた頃でしょうか?
GWは最大9日間と言われる今年。
うちはカレンダー通りですが、何か?!という方々も、
やっぱりこの時季はウキウキしているのでは?
さて、4月に入って列島は相変わらずに異常気象に見舞われ、
夏日の翌日が冬日、みたいな、やっかいな日々が続いておりました。
それでもやっと初夏らしい陽気が定着した今日このごろ。
慌てクローゼットにしまいこんでいた夏物を取り出している状況です。
去年、活躍してくれた麻のシャツ。
1年前の初夏から夏にかけての日々が思い起こされます。
麻の服はいつでもひなたのにおいがします。
洗えば洗うほど肌に馴染んで着やすくなるのが麻の魅力。
麻を使った生活用品とヒトの歴史は古く、
日本でいえば麻縄は縄文時代から、
衣服は弥生時代から使われていたと見られ、
当時の遺跡から麻を使ったものが発掘されているとか。
日本のみならず、世界中で麻はもっとも古いつきあいのある繊維で、
しばしば神事に関係する衣服や用品に使われていたのも、
世界で共通しているようです。
繊維として質や見た目がよく、
丈夫であることもその要因だったかもしれませんね。
人類と麻は、もう1万年もつきあっていることになります。
現代の麻といえば、リネン(亜麻=フラックス)またはラミー(苧麻=イラクサ)、
ヘンプ(大麻)。
いずれも、茎の表面にある繊維を収穫して糸に仕上げます。
質感や肌触りに野性味があるラミーや大麻に比べて、
リネンは光沢や質感、肌触りも抜群で、いかにも上質な繊維です。
高級品は絹と同じ値段になると言われます。
ちなみに、現代では何かと世間を騒がせることの多い大麻は、
日本では古くから衣服や神事の用品の素材として使われていました。
日本の大麻は幻覚作用の成分が少なく、
もっぱら繊維に加工するために栽培されていたようです。
麻の質は原料と、その原料を糸にする技術、糸を繊維にする技術の
すべてが整わないと高級素材にならないのはもちろんですが、
とくに原材料の質と紡績技術が仕上がりを大きく左右すると言われます。
現在、リネンの原料となる亜麻=フラックスの生産地はおもに、
フランス北部やベルギー、ロシア、東欧諸国、中国。
とくにフランス産のフラックスは上質とされます。

素材としての麻の特徴で、まずあげられるのが涼しさ。
麻の生地に触れると、感触がひんやりしています。
加えて、天然の植物繊維ならではの通気性や吸湿性があり、
汗などの水分が蒸発しやすく乾きやすいという利点もあります。
要するに、蒸し蒸しして高温多湿な日本の夏には最適な素材なのです。
最近は、そうした性質を持つ化学繊維がたくさんありますが、
やはり天然素材の肌触りは格別。
しかも、100%の化学繊維のシャツとはまったく異なる、
高級素材としての格があります。
そんな日本の夏の強い味方、麻のシャツのシーズンがやってきました。
土井縫工所の麻のドレスシャツは、
高級リネンの代名詞であるHerdmans Linenを使用。
フランス産の良質な亜麻=フラックスを原料に、
伝統的なアイリッシュリネンの紡績技術を用いて織られた生地です。
吸湿・速乾・通気性に優れていることはもちろん、
上質なリネン生地特有のネップや節が、質感に味わいを与えています。
その天然の風合が生む色気は、ほかの素材には見られないもの。
大人の男の魅力がその素材から匂い立つような、リネンのドレスシャツ。
今季はとくに、毎シーズン人気の定番色、ホワイトやブルーに加え、
今もっとも注目されているカラーである、ビビッドなイエローが新登場。
ノリをきかせてピシッとさせたスタイリングで、
ブリティッシュをキメるもよし、
洗いざらして独特の風合いや風格を見せて
イタリアンを楽しむスタイリングもよし。
爽やかで元気が出るイエローやブルーを
今夏のコーディネートのポイントにしてみては?
また、今回は夏のドレススタイルに最適なレノクロスも登場。
生地を交互に絡ませながら織る特殊な素材のレノクロスは、
生地の目が粗くなり、特有の凹凸感とメッシュ構造を持ちます。
そのため通気性がよくなり、伸縮もしやすく
シワにもなりにくいという、
ビジネスシーンのお役立ち素材といえます。
土井縫工所ではさらに、国内最高クラスのコットンである、
ロイヤルカリビアンコットンで織り上げたレノクロス素材を採用。
仕立てはもちろん土井縫工所ならではの上品なドレス仕様で、
快適さと上品さを両立したワンランク上の製品になっています。

今年もまた猛暑という長期予報が出ています。
オンタイムのクールビズにもオフタイムのドレスカジュアルにも、
幅広く対応できるリネン&レノクロスのドレスシャツは
夏の最強アイテムです。
強いうえにエレガントな武器で、夏も涼しげに!