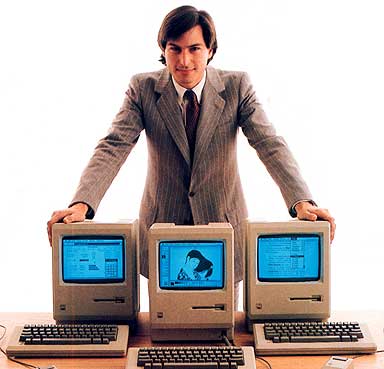(写真はNASA提供)
宇宙の果てってどうなってるんだろう?
そもそも宇宙に「果て」はあるのか・ないのか?
子どもの頃、「果て」を考えると、いいようのない不安に襲われたものです。
ともあれ宇宙好きで、ハインラインとかの少年少女向けSF小説を読みあさっていました。
先日、スペースシャトル「アトランティス」の打ち上げがありました。
打ち上げから2日後、シャトルは無事に宇宙に浮かぶ国際宇宙ステーションに到着し、
ドッキングも成功。
開始以来30年を経たスペースシャトル飛行計画も終止符が打たれ、
これがシャトルにとって最後の飛行になりました。
スペースシャトルといえば思い出されるのが、1986年のチャレンジャーの事故です。
あの日、打ち上げを現地で見守っていた人、あるいは実況中継をテレビで見ていた人達の目前で、
大空をグングン上昇して行ったチャレンジャー号。
アラビアのモスクに巨大な蛾が張り付いたようなシャトルの姿は、
どこか厳かで空飛ぶ寺院のようにすら見えました。
次の瞬間(正確には打ち上げから73秒後)、私たちが見たのは、
青い空を背景に音もなく白煙が盛り上がっていく光景でした。
それは長く首を伸ばした白鳥のようなシェイプを描きながら、
モクモクと成長していきました。
何が起こったのか、世界中が呆然となっていた最中、管制官の声が聞こえたのです。
“”The vehicle has exploded. Flight controllers are looking very carefully at the situation.”
「乗り物は爆発しました。私たちは状況を注意深く見守っています」
そのクールな口調は当時の私に、世界一落ち着いている男と思わせてくれました。
SF映画「2001年宇宙の旅」に、HALというコンピューターが登場します。
彼は非常に優秀な人工知能で、しまいには人のような感情をもち、
意のままにならない他者を排除しようと殺人すら犯します。
しかも、悪事がばれて彼の生命維持装置である電源が切られそうになると、
歌を歌って相手の情けにすがるという、きわめて人間的な手段に出ます。
そんなHALは、ヒトのような感情を持ちながら、決して激することなく、
その口調は常に冷静沈着です。
チャレンジャーの事故を伝える管制塔のヒトは、
本当にHALさながらの落ち着きっぷりでした。
誤解を恐れずにいうなら、爆発の映像の美しさとクールな口調が妙にシンクロして、
あの事故は記憶に強く刻まれています。
ともあれ、この事故と2003年に再度起こった事故によって、
スペースシャトル計画は終息へと向かわざるを得なかったと言われています。
そんな事故から25年。再び実況中継された最後の飛行。
この四半世紀で、アメリカも世界も大きく変わり、そしてもちろん、
日本はここにきて大きく変わりました。
ここからの近未来、世界はどんなふうに変わっていくのでしょうか?
宇宙や近未来を描いたSF映画のランキングが、先日英国の映画雑誌で発表されました。
そのベスト3は、
1位・ブレードランナー
2位・スターウォーズ・帝国の逆襲
3位・2001年宇宙の旅
というラインナップでした。
ブレードランナーが1位というのが、ちょっと意外な気がします。
鬼才リドリー・スコットの監督作品でとても好きな映画だし、
近未来の街の舞台がトーキョーもどきというのも日本人としては親近感を覚えるし。
でも1位というのはアリか?
やっぱりイギリス人のサブカル好きというか、へそ曲がりというか。
この映画、日本で投票したら絶対1位にはならないんじゃないかと思います。
2位の帝国の逆襲。宇宙もの近未来ものといえばお子様向けが多かった時代に、
子どもだましでないマジなSF映画が出てきたと思わせてくれた作品です。
ワクワクさせてくれると同時に、すべての造形がものすごくアーティスティックで、
普通でいえばこっちが1位のはず。
そして3位の「2001年宇宙の旅」は、SFとかの枠を取り去っても私の中で名作中の名作。
誰もが抱く(であろう)宇宙の神秘への好奇心や恐れをこれほど如実に哲学的に、
かつ造形的に描いた映画は、これがはじめてではないでしょうか?
しかも、何がすごいって、宇宙を静かに進んでいく宇宙船の映像に合わせた音楽が、
近未来的な電子音などでなく、優雅な「美しき青きドナウ」。
そしてメインタイトルのBGMは「ツァラトストラはかく語りき」。
前編通してクラシックの名曲が選ばれています。
近未来の映像にあえて古典的な音楽を合わせる事によって、
空間が時間的な縛りから解放されているのでした。
そして、さらに「2001年〜」が画期的なのは、
宇宙船の乗組員が宇宙服ではなく、ポロシャツを着ていること。
もう、はじめてこれを見た時は、まさに目からウロコでした。
近未来を表す際にはスペーシーな服というのが長年のお約束であったはずなのに、
監督であるスタンリー・キューブリックは真逆のことをやってのけたのです。
つまり、宇宙船の中で普段着のカジュアルウェアを着ていられることこそ、
科学が進歩した近未来での環境なんですよ、ということを示したのでした。
そのアプローチは当時本当に新しくて、
2001年は宇宙でポロシャツなのだと私は軽い感動を覚えたものです。
そして今、遠い宇宙から送られてくる映像を見ると、
国際宇宙ステーションの中の人たちはポロシャツやラガーシャツ、
ドレスシャツといたって普通。
短パン着用の人もいて、スペース・クールビズなのでした。
「2001年〜」というのは映像的にも優れた映画だけれど、
音楽やファションという時代の影響をうけやすい分野において、
普遍のものを選ぶことで古くなることを回避しています。
だからこそ、この映画はいつ見ても新しくて斬新なのだと思います。
その点、ブレードランナーは時代を感じさせる映画です。
そのあたりもおもしろいけどね。
個人的にはSF映画といえば「バーバレラ」や「A.I.」「地球に落ちて来た男」を入れたいところ。
10位内に「未知との遭遇」が入っていないのも不思議です。
それまで宇宙人といえば「侵略者」だったのが、はじめて友好的な宇宙人を描いた
ということでは画期的だと思うのですが。
一方「バーバレラ」は、ポップでファッショナブル、かつエロティックなSF映画です。
その後政治活動にのめりこんで闘士になってしまったジェーン・フォンダが、
まだ若く美しくセクシーな女優で、
ロジェ・バディムというこの映画の監督の愛妻だった頃の作品。
ジェーン・フォンダの美しさと抜群のスタイルとコケティッシュな魅力が堪能できる逸品です。インテリアや衣裳も今見るといかにもシクスティーズなレトロモダンでおもしろい。
古き良き近未来の世界観をたっぷり楽しめます。
ちなみに悪の女王的な役どころで登場するアニタ・パレンバーグは、
ローリング・ストーンズの伝説的初期メンバー、故ブライアン・ジョーンズの元恋人で、
その後キース・リチャードの恋人になったヒト。
中性的な美貌で、美青年のブライアンとは「双子みたいなカップル」と言われていました。
近未来映画ながら、60年代当時のヨーロッパのヒップな空気が伝わってくる作品です。
一方「A.I.」は、感情を持ったロボットとヒトとの交流を描いたSF作品。
これはスタンリー・キューブリックが温めていた企画だそうで、
その意志を継いで親交のあったスピルバーグが脚本・監督・制作を手がけた作品。
とくにロボットの息子とヒトの母親との別れは、涙なくしては見られません。
さすがキューブリックの元ネタという、「2001年〜」に通じる哲学的な匂いのする作品です。
後半ちょっと「長・・・」と思いましたが。
「地球に落ちて来た男」はニコラス・ローグの監督でデヴィッド・ボウイ主演、
1976年のイギリス映画です。
宇宙から「落ちて」来て、帰れなくなった男の物語なのですが、
カフェで飲んだくれている宇宙人というのが斬新な作品でした。
ともあれ、時代とともに、近未来の捉えかたは当然変わってきます。
「2001年〜」や「バーバレラ」が作られた1960年代後半から見れば、
40年後の現代はまさに近未来。
ロケットは確かにあって宇宙ステーションもあるけれど、
あの時代に予測したほどは発達していません。
その変わり、当時はその片鱗もなかった、ケータイ電話が見事な発展を遂げています。
ピエール・カルダンが宇宙ルックを提案したのが1968年でした。
そして、アポロ11号が月面着陸を果たし、人類がはじめて月に立ったのが1969年。
「人類にとっての偉大な一歩」を刻んだ飛行士が、
月面に星条旗を打ち立てたのを見た時、
誰のものでもない美ししいものを誰かが勝手に「俺の!」と言って、
ワシづかんでしまったような、軽い不快感を感じました。
もう今となっては、国際宇宙ステーションでミッションを遂行する日本人の姿も見慣れ、
アメリカでも日本でもどっちでもいいやという気になっていますが。
原発の事故直後、この事態がもっと悪化したら、
もう地球上どこに逃げても放射線から逃れられないなどと言われたものです。
こうして人類は地球を追い立てられていくんだろうか、
でも、まだ全然準備が整っていないじゃないと思ったものです。
そう、「2001年宇宙の旅」では人類は月に移住しているけれど、現実ではまだまだ。
月面でポロシャツやドレスシャツを着て暮らせるようになるまで、
なんとか地球をもたせて欲しいものです。
ちなみに「史上最高のSF映画ベスト10」は、下記の通り。
1位『ブレードランナー』(82)、
2位『スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲』(80)、
3位『2001年宇宙の旅』(68)、
4位『エイリアン』(79)、
5位『スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望』(77)、
6位『E.T.』(82)、
7位『エイリアン2』(86)、
8位『インセプション』(10)、
9位『マトリックス』(99)、
10位『ターミネーター』(84)
まあ、古いのばっかり。
近未来に思いを馳せていた、あの頃が懐かしいという結果のような気がします。